
派遣社員の育休、あきらめないで!取得条件から手続き、復帰後の働き方まで徹底ガイド
- コラム
はじめに
「派遣だから育休は無理」と不安に感じるあなたへ。妊娠が判明し、出産を控えているけれど、派遣社員という雇用形態で育児休業が取得できるのか不安に思っていませんか?結論から言えば、派遣社員でも育休を取得することは可能です。しかし、正社員とは異なる条件や手続きの注意点もあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。この記事では、派遣社員が育休を取得するための制度、条件、必要な手続き、もらえるお金、そして職場復帰後の働き方まで、すべてを徹底解説します。これを読めば、あなたの育児休業に対する不安が解消され、安心して出産と子育てに臨めるはずです。
派遣社員でも育休は取れる!まずは条件を知ろう
育児・介護休業法で定められた育休の基本は、育児休業は男女問わず取得できる権利である、ということです。労働者は、原則として子どもが1歳になる前日まで休業できる制度です。期間の延長も可能なケースもあります。育児・介護休業法は2022年4月に改正され、より育休が取得しやすくなるよう制度が変更されました。では、派遣社員が育休を取得するための条件は何でしょうか。
派遣社員が育休を取得するための3つの条件
派遣社員が育児休業を取得するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 同じ派遣会社に1年以上継続して雇用されていること:育休の開始予定日時点で、雇用契約が1年以上継続している必要があります。これは、労働基準法における労働者としての権利を保護するための要件の一つです。
- 子どもが1歳6ヶ月になる前までに雇用契約が終了しないことが明らかであること:育児休業の期間中も雇用関係が継続する見込みが必要です。契約期間の定めがある有期雇用の派遣社員の場合は、特に注意が必要です。契約の更新によって育休取得が可能となる場合もあるため、派遣会社に事前に確認しましょう。
- 週2日以上働く日数が定められていること:育児休業は、週2日以上勤務している労働者を対象としています。非常勤や短時間勤務の方も、この条件を満たせば対象となります。
雇用期間の定めがある場合(有期雇用)の注意点
有期雇用である派遣社員の場合、育休取得には契約期間が大きく関係してきます。育休開始予定日の時点で雇用契約が1年以上継続しており、かつ、子どもが1歳6ヶ月になる前までに雇用契約が終了しないことが明らかであることが求められます。契約の更新を繰り返して勤務している方は、更新の状況によって育休が可能な場合もあるため、派遣会社の担当者に相談し、今後の契約更新の方針について確認しておくことが重要です。労使協定で定められている場合は、条件が緩和されるケースもあります。
派遣社員が育休を取得できないケース
上記の条件を満たせない場合や、労使協定によって育児休業を取得できない者として定められている場合、育児休業の対象とならない可能性があります。例えば、勤務期間が1年未満の場合や、契約の更新が難しいと判断された場合などが該当します。しかし、個別の状況によって対応が異なることもあるため、諦めずに派遣会社に直接問い合わせて確認することが大切です。

育休でもらえるお金、損しないための知識
育休中は給与の支払いがなくなるため、お金の心配をされる方も多いでしょう。しかし、育児休業給付金など、育休中に受け取れる給付金や手当があるので安心してください。正しく制度を理解し、損しないための知識を身につけましょう。
育児休業給付金とは?いくらもらえる?
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に支給される給付金です。支給の目的は、育児休業中の生活を支援し、安心して子育てができる環境を整えることです。
- 給付額の計算方法と支給期間:育児休業給付金の額は、休業開始時の賃金日額を基礎として計算されます。原則として、休業開始から180日間は賃金月額の67%(上限あり)、それ以降は50%(上限あり)が支給されます。支給期間は子どもが1歳になるまでですが、保育所に入所できない場合など、一定の条件を満たせば最長2歳まで延長可能です。双子など多胎妊娠の場合は、特例もあります。
- 給与計算期間と支給タイミング:育児休業給付金は、2ヶ月ごとにハローワークから支給されます。申請から初回の支給まで時間がかかる場合があるため、事前に確認し、資金計画を立てておくことが大切です。
社会保険料の免除について
育児休業中は、健康保険と厚生年金保険の社会保険料が免除されます。これは雇用保険とは別の制度で、労働者本人の申請によって適用されます。免除の期間は、育児休業開始から終了までの間です。社会保険料の免除は、育休中の経済的な負担を軽減する大きなポイントとなるでしょう。派遣会社が手続きを行ってくれることが多いですが、自身でも確認しておくと安心です。
育休中の税金はどうなる?
育児休業給付金は非課税所得のため、所得税や住民税がかかりません。そのため、育休中は所得税の源泉徴収は発生せず、住民税の支払いも減額されたり、翌年度から非課税となる可能性もあります。ただし、前年度の所得に応じて住民税が課税されるため、注意が必要です。詳細は管轄の市区町村に問い合わせるのがいいでしょう。
「実質10割」って本当?育休中のお金に関するよくある誤解
育休中に「実質10割」の収入があるという話を耳にすることがあるかもしれません。これは、育児休業給付金(手取り賃金の約8割に相当)に加えて、社会保険料が免除されることで、手元に残る金額が休業前の手取り給与とほぼ同等になるという意味で使われる言葉です。給与から天引きされていた社会保険料がなくなるため、実際に使えるお金が増えるという感覚に近いかもしれません。しかし、額面給与がそのまま支給されるわけではないので、この点は誤解しないように注意しましょう。
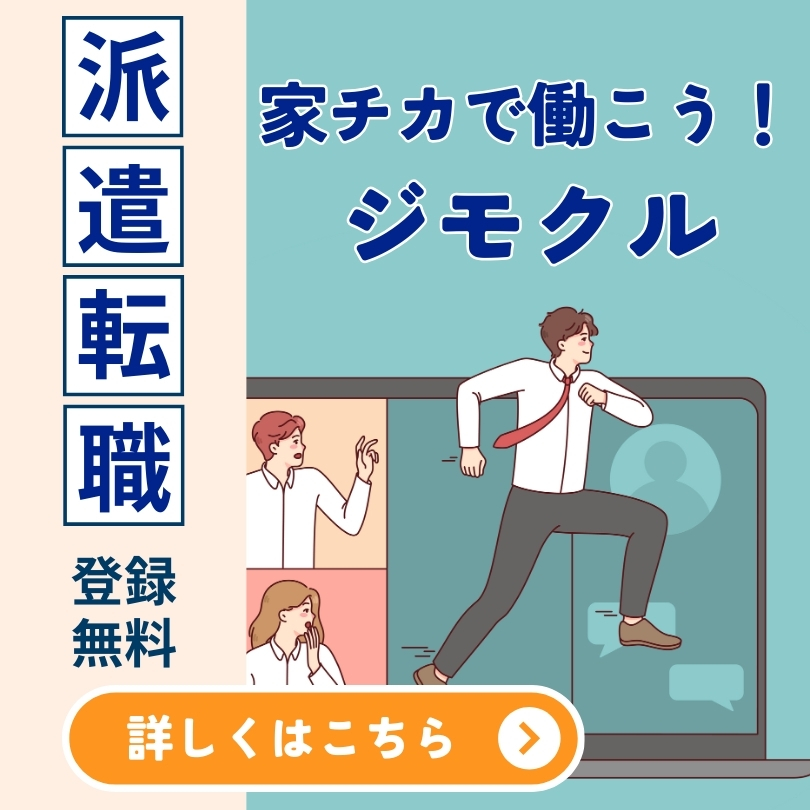
育休申請から復帰までの流れと手続き
育休をスムーズに取得し、職場復帰するためには、事前の準備と適切な手続きが重要です。派遣社員の場合は、派遣会社と派遣先企業それぞれに対する対応が発生します。
育休取得の相談、いつ、誰にすべき?
育休を希望する場合、できるだけ早く、妊娠が判明した時点で派遣会社に相談することをおすすめします。遅くとも、育休を開始したい日の1ヶ月前までには申し出が必要です。
- 派遣会社の担当者への相談:まずは派遣会社の担当者に連絡し、育休の取得を検討している旨を伝えましょう。担当者が今後の流れや必要な書類について詳しく説明してくれます。派遣会社によっては、育児休業に関する専門の部署や相談窓口を設けている場合もありますので確認してみるといいでしょう。当社でも育児関連の支援を行っています。
- 派遣先企業への連絡:派遣会社を通じて、派遣先企業にも妊娠と育休取得の意向を伝えることになります。派遣先企業の業務状況や後任の手配などを考慮し、引き継ぎなどをスムーズに行えるよう、早めの連絡が望ましいです。
育児休業申出書の提出手順
育児休業の申請は、原則として休業開始予定日の1ヶ月前までに派遣会社へ育児休業申出書を提出することで行います。必要な書類は派遣会社によって異なる場合があるため、担当者の指示に従いましょう。一般的には、医師の診断書や母子手帳のコピーなどが求められることが多いです。
育休期間の決め方と注意点
育児休業の期間は、原則として子どもが1歳になるまでです。出産後8週間は産後休業期間であり、この間は育休とは別の制度となります。育休は産後休業終了の翌日から開始できます。保育所の入所が困難な場合など、一定の条件を満たせば最長2歳まで延長が認められます。育休の期間を決める際には、保育園の状況や家庭の事情、職場復帰のタイミングなどを総合的に考慮することが大切です。また、2022年10月の改正により、育休の分割取得が可能となりました。夫婦で育休を取得する「パパ・ママ育休」を検討する場合も、派遣会社に相談し、詳細を確認しましょう。
育休中の契約満了や更新に関するポイント
育休中に契約期間の満了が来る場合、契約更新の有無が心配になることでしょう。育児・介護休業法では、育児休業中の解雇は原則として禁止されています。しかし、契約の更新については、派遣会社と本人の雇用契約内容や派遣先企業の意向によって異なります。育休取得の申し出があった時点で、派遣会社は今後の契約について本人と話し合う義務があります。育休を取得したい意思を明確に伝え、契約更新の見込みについて確認することが重要です。万が一、契約の更新が難しい場合でも、次の仕事の探し方など、キャリアに関する相談に乗ってくれる派遣会社も多いです。
育休復帰後の働き方と注意点
育休を終え、職場復帰する際には、新しい生活リズムに慣れることや、仕事と子育ての両立に向けた準備が必要となります。派遣社員として働く方も、支援制度や働き方の工夫を知っておきましょう。
職場復帰に向けた準備と相談
育休終了が近づいてきたら、派遣会社の担当者と職場復帰についての面談を行いましょう。復帰の時期や希望する働き方(時短勤務、残業の有無など)、新しい仕事の紹介などを相談できます。派遣会社によっては、復帰前の研修や情報提供といったサポートを行っている場合もあります。復帰後の仕事内容や勤務時間など、自身のスキルや希望に合う求人があるか確認する良い機会です。
時短勤務やその他の制度利用について
育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを持つ労働者に対して、短時間勤務制度(時短勤務)の利用を義務付けています。派遣社員もこの制度の対象者となります。時短勤務を希望する場合は、派遣会社に申し出ることによって、所定労働時間を短縮して働くことが可能です。また、子の看護休暇や時間外労働・深夜業の制限など、子育てと仕事を両立するためのさまざまな制度があります。これらの制度の内容や利用方法を知って、自分の状況に応じて活用しましょう。
復帰後の仕事探し、キャリアについて
育休明けに同じ派遣先へ戻ることもあれば、新しく仕事を探し直すこともあるでしょう。派遣会社は、復帰後のあなたのキャリアを継続できるよう、希望に合う求人を紹介してくれます。在宅勤務や残業少なめの事務職種、IT系のエンジニア職や営業職など、多様な職種の求人があります。子育てと両立しやすい働き方を見つけるためにも、派遣会社のサポートを積極的に利用しましょう。未経験でもスタートできるお仕事も多いです。

派遣会社選びも育休取得の重要なポイント
育児休業をスムーズに取得し、復帰後も安心して働くためには、信頼できる派遣会社を選ぶことが非常に重要です。育休に関する知識やサポート体制が整っている派遣会社を選ぶことが、成功の鍵となります。
育休制度が充実している派遣会社を見つけるコツ
育休制度が充実している派遣会社を見つけるには、以下のポイントに注意して情報を集めましょう。
- 育休取得者の声や体験談を確認する:派遣会社のウェブサイトや口コミサイトで、実際に育休を利用した派遣社員の声や体験談を参考にしましょう。
- 担当者の対応を見る:登録時や相談時に、担当者が育休に対してどれだけ知識があり、親身になって相談に乗ってくれるか確認することも大切です。
- 福利厚生やサポート内容の一覧を確認する:育児休業給付金以外にも、子育て支援サービスやキャリア相談など、どんな福利厚生やサポートがあるか詳しく確認しましょう。
担当者との信頼関係の築き方
派遣会社の担当者との信頼関係は、育休をスムーズに進める上で非常に重要です。妊娠が分かった時点で早めに報告し、育休を希望する意思を明確に伝えましょう。不明な点や不安な点は遠慮なく質問し、丁寧なコミュニケーションを心がけることで、担当者もあなたの状況を理解し、最大限のサポートを提供してくれるでしょう。ジモクルには、相談しやすい担当者が在籍しており、専任の担当者が求職者の希望や不安に対応してくれるため、安心して就職活動ができます。また、労働条件が明確な求人を提供し、働きやすい環境を確保できるよう派遣先企業との連携も密に行っています。
執筆者:家チカで働こう! ジモクル
(武蔵ロジスティクス株式会社 人材サービスグループ)
菅原 隆
〒143-0004
東京都大田区昭和島1丁目2番8号 昭和島ロジテムセンター
TEL:0120-200-450
